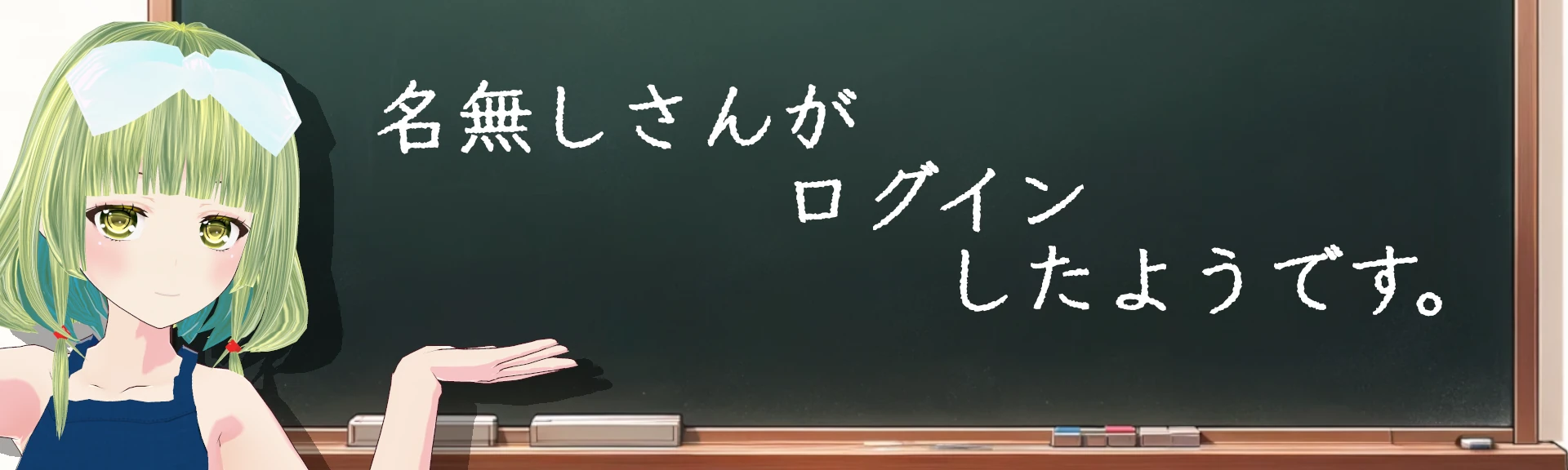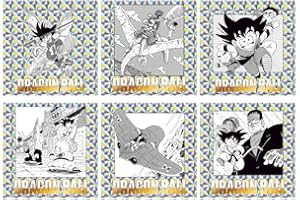BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MM DAEMON X MACHINA TS オプションパーツセット WEAPON SET 01 色分け済みプラモデル
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) 30MM エグザビークル(水中探索メカVer.) 1/144スケール 色分け済みプラモデル
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) HG 機動戦士ガンダムSEED DESTINY グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機) 1/144スケール 色分け済みプラモデル
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)

BANDAI SPIRITS(バンダイ スピリッツ) HG 機動新世紀ガンダムX ガンダムレオパルド 1/144スケール 色分け済みプラモデル
商品ページAmazon
収益広告(自動登録)
サクラ度:△(要確認)
CPUの性能指標
概要
CPUにはいくつかの性能指標があるが、それについて代表的なものについてまとめた。
最初に
最初に以下の英単語を覚えておいた方がよさそう(意味を覚えるというより、これらの英単語が出てくるということを覚えておく)。
後に出てくるCPIとMIPSの混同が避けられる。
・Instruction(命令)…CPUが実行する命令のこと
・Clock cycle(クロックサイクル)…クロック数
・Million(ミリオン)…100万
・Second(秒)…秒数
・Per(パーセント)…パーセント
性能指標
代表的な指標は以下3つ。
・クロック周波数(クロックサイクル時間)
・CPI
・MIPS
クロック周波数とクロックサイクル時間
一つ目が「クロック周波数」。
その名の通り、1秒あたりのクロック数を表す。
似た指標に「クロックサイクル時間」というものがある。
これは1クロックあたりにどれだけ時間がかかるかを表す。
「クロック周波数」とは逆数の関係になる。
CPI(Clock cycles Per Instruction)
2つ目の性能指標は「CPI」。
1つの命令あたりに何クロックが必要かを表す。
MIPS(Million Instruction Per Second)
前述の「クロック周波数」と「CPI」でCPUの性能を表すには問題がある。
それは例えば、「クロック周波数」が従来の2倍を持つCPUでも「CPI」が10倍(=1つの命令を行うのに10倍のクロック数を要する)だった場合、行える命令数が1/5になってしまうということ。
この問題を解決する性能指標が「MIPS」。
「1秒あたりに行える命令数」を表す。
クロック周波数÷CPIなどで計算できる。
命令ミックス
「CPI」と一言でいうがこれ自体の測り方で差が出てしまう。
CPUのすべての命令が同じクロック数を要するわけではないため、例えばAという命令では3クロックで十分だが、Bでは4クロック必要という場合、小さい方の3クロックで「MIPS」を計算した場合、実態の数値とは乖離が出てしまう。
それに対する解決策が「命令ミックス」というもの。
あらかじめ各命令の出現頻度を定めておいて、それを基に各クロック数の出現頻度を計算することで、同じ基準かつ実態に近い数値で「CPI」を測ることができる。
例えば
| クロック数 | 出現頻度 |
|---|---|
| 3 | 0.2 |
| 4 | 0.8 |
という場合、
CPI = 3 × 0.2 + 4 × 0.8 = 3.8
としてCPIを算出することができる。
コメントログ
コメント投稿
管理人ツイート